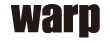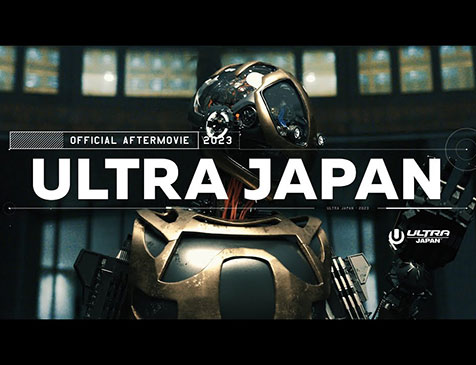ビジュアル&サウンドブック「Cotton fields 」発売記念スペシャルインタビュー・長濱治氏に聞くブルーズの旅
2 0 2 0年2月2 2日、長濱治氏の写真とピーター・バラカン氏のテキストによるビジュアル&サウンドブック『Cotton Fields(コットンフィールズ)』(TWJ BOOKS)が発売する。フィルムというアナログカルチャーの素晴らしさを、フィルムインスタレーションを施した最新の技術でu p c y c l eした本作。テキストにはルーツミュージックに造詣が深いピーター・バラカン氏がテキストを書き下ろし、加えて、彼の選曲によるブルーズからそれに影響を受けたロックまでの曲が聴けるSpotifyコードを付けた「見る」「読む」「聴く」ことができるアートブックとなる。
新型コロナウィルス感染症に伴い、3月6日に代官山蔦屋書店にて予定されておりましたイベントは延期となりました。
延期の日程等は分かり次第当サイト、または代官山蔦屋書店のウェブサイトにて告知いたします。
「Cotton Filed」発売を記念したイベントを開催予定!
https://www.warpweb.jp/culture/news/book/37724/

Interview text: Fuyuko Kita
今回warpでは長濱氏にブルーズの旅のインタビューを敢行した。1960年代後半から雑誌や広告写真で活躍していた写真家・長濱治氏は、50歳を目前にして、「いま、自分か”本当に好きなものを撮っておかなければ”、もう撮れなくなる」、という思いに駆られて、ブルースマンの素顔を撮影するため、ブルースの聖地・アメリカ南部の「cotton fields(綿花地帯)」に、プライべートな旅に出る。4年間に10回、アメリカのディープサウスエリアに通い、70人余のブルーズマンと出会い、 42000カットのフィルムが残った。今回の写真集もそうだが、彼の写真には音楽という情景がみえる。音楽はどうやら欠かせない要素のようだ。

心が締め付けられるような感覚があるというのを子供心に体感しちゃったんだよね。
「音楽はいつもあったからね。レコードもつねに家にあったし、カメラマンはなんとなくなっちゃったんだけど。中学のときに聴いたベニー・グッドマンやグレン・ミラーとか洗練された音楽だなという感覚があった。なぜかというと今回の本の原点となるベースの音がブルーズなんだと思う。なんだかちょっとブルーになったりさ、心がなんか締め付けられるような感覚があるというのを子供心に体感しちゃったんだよね。」

ブラックパンサーはいまいちピンとこなくてね。ふっと思ったときに観た映画が、『ミシシッツピー・バーニング』
アメリカの黒人音楽のルーツを撮るべく80年代に南部に行った経緯についても聞いてみた。
「その話の前になるけど、まずはね、アメリカの60年代、カメラマンになろうかどうかと考えながら3ヶ月ぶらぶらしていたときにバイカーのギャングに興味をもっちゃった。アメリカの典型的な家庭とは反対の労働者やカウボーイたちだね。1966年だったけど、やばい連中だから、カメラ向けるなと言われた。で、撮らなかった。2年後にニューヨークに行って撮ったわけなんだけど、アメリカの中産階級でバックグラウンドは都会で、はぐれもの、ちょっとロマンがあるストーリーが頭にあった。たぶん大学のときにエド・ファン・デア・エルスケンのパリの娼女を撮った「セーヌ左岸の恋」の影響かな。写真って、こんなことできるんだって思った。あと、影響受けたゴダール、トリフォーの感覚とどこかでオーバーラップしたと思う。そんな感覚を探りながら撮ったのが、ニューヨークのバイカーだった。」

黒い血を吸ったのが、白い綿になっているイメージをしてね。
「次に撮ろうと思ったのは、白人ではなく黒人社会のなにか。ブラックパンサーはいまいちピンとこなくてね。ふと思ったときに観た映画が、『ミシシッツピー・バーニング』。公民権運動の始まりとなった事件だけど、(1964年に米ミシシッピ州フィラデルフィアで公民権運動家3人が殺害された事件をモデルにしたノンフィクション映画。1988年公開。アカデミー撮影賞受賞作品。)ジーン・ハックマン!すごかったね。」
「あの映画を観てアメリカの南部、ディープサウスという土地、白いコットンが咲き乱れているあの土地、白いコットン=白人たちがお金をつくる、その下には黒人の労働者たちのしかばねが入っていると頭のなかで想像した。血を吸ったのが、白い綿になっているイメージをしてね。」

ブルーズマンの7割はクラークスデールの一帯から出ているんだ。
「映画を観てね、わ、これすごいわ、行きたい、行きたい。でもなんで行きたいんだよ。黒人撮る。おれジャズ好きじゃん、ブルーズじゃん。ひらめいたんだ。最初はひとりで行ったけど、思うブルーズマンに会えなくて、アメリカの友人に電話して。どうだって聞いたら、いまの時代はそんなにやばくないだろって。ミシシッピ州のジャクソンで合流して車で行った。2度目に行ったときに若い青年が紹介してくれた一番深南部のクラークスデールという町のレコード店をやっている白人の親父が、僕のことに興味を持ってくれて付き合ってくれて、いろいろと教えてくれたんだ。」
「ミシシッピ州のデルタ地域にあるクラークスデールは東京都の広さぐらいの地域に著名なB.B.キングとか、マディ・ウォーターとか、ティナ・ターナーとか、ベッシー・スミスとか、ブルーズマンの7割はそこの一帯から出ているんだ。あ、あいつはあっちの路地の一家だよという感覚なのよ。」
ブルーズマンはモテる。女の彼氏がやきもちを焼いて襲ってくるので護身用にナイフとかピストルを持っていたらしい。

Jack Owens
「ブルーズを勉強している青年が連れて行ってくれたんだけど、死んでいると思ったジャック・オーウェンスに生きている間に会うことができた。彼は普通のテラスでロッキングチェアで座って待っていたね。(写真の)服装が全米を回っているときのステージの正装で、脇にピストルが入っている。ブルーズマンって女の子にモテるんだって。そうすると、その女の子の彼氏なんかが、やきもちを焼いて、ステージが終わると襲ってくるので護身用にナイフとかピストルを持っていたらしい。だからブルーズマンって体に傷を持っている人が多いんですよ。顔を切られているとかさ。僕が見ていても爺さんでもモテていたね。」

James San Thomas
「そう、ジェームス・サン・トマース(上写真)はレーガン大統領のときのホワイトハウスの独立記念日の晩餐会で演奏している。」
偉大なミュージシャンなのにこんなみすぼらしい家に住んでいるのかと目を見張っていたら、長濱氏は話を続ける。
「あ、これね、「ショットガンハウス」って言って、入り口開けると台所と居間とベッドルームだけ。ショットガンで打つと裏庭まで突き抜けるくらいの粗末な家なわけ。こういうところ住んでいる。2、3度行ったけど、いい感じなんだよ。お礼にいつもお酒と20ドルを持って。ゆっくり座ったりして、いつ生まれて、若いときから貧乏で、そんな話して。ところがこの人はね、ギターをやってブルースを歌っているんだけど、彫刻をやったり、絵を描いているの。ここに棺桶があるんだけど、十数年前に亡くなった愛する妻の亡骸を彫刻にしてミイラみたいな人形にして、女房と一緒だって言ってたね。この話には後日談があって、芸術家の息子がひとりいるんだけど、銀行通帳が出てきたらしいんだ。その額が何十万ドル(何千万円)も入っていたんだって。そいうことを後で聞いたよ。」

人間は目なんだよ。カメラ持っているだけじゃダメでしょ。ニコニコ笑いながら撮る
長濱氏が撮る写真はなんといっても人物の目線が印象的だ。平凡な暮らしをしている人でも「カリスマ性」と「魂」をあぶり出し人間としての力強さを映し出す。そして、被写体は、完全なる他人だ。一体どのように撮るのだろうか。
「おばあちゃん「どうも」とか、怖そうなおじさんでも、「どうもどうもハラショー」って言ってしゃべりながら撮っているからさ。いきなりではなくて「ジャンボー」とか、ニコニコ笑いながら撮ると、なんなのっていうところをバッバッと撮ることばっかやってきたの。まあ、最初は嫌だったよ、怖いし、知らない人だから。それやらないとカメラマンになれないかなと思って。笑いとか喋ったりするのがいいんだよね。カメラマンから心開いてやってきた言わばパパラッチだよ。」
「人間は目なんだよ。カメラを持っているだけじゃダメでしょ。カメラが見えなくなるぐらい、持っている人が前に出てくれば、向こうも驚いたり、おもしろがってくれるでしょ。カメラを持つってことはピストルと一緒だから向こうにとっては怖いこと。動物はまた違った意味で怖いけど、風景を撮ったり、頼まれて撮るというのは、はっきり言って楽なの。ヘルズエンジェルスも最初は怖くてやばかったけど、徐々になかに入って、仲良くなって結局向こう側に入っちゃうから同じ立ち位置になる。そうすると目線が来る。」
「カメラ自身は非常に怖いということをちゃんと知っておくこと。で、よりいい人間の写真を撮りたいと思ったら、望遠レンズでさっと撮る。いただくみたいな。盗むわけだよ。それより前に出てやることはワイドを持って1メートル、2メートルでも近づいて撮れ。怖い人でもね。それができたら撮れるよ。」

写真(『Cotton Fields』 )からは歌は聞こえてこないけど、音は聞こえてくる。
そして、長濱氏が写真を撮ったあと、素敵な後日談がある。
「場所は定かじゃないけど、ロバート・ジョンソン、チャリー・パットンのお墓が建てられていた。レコード屋の親父によると、(エリック・)クラプトン、Z.Z.トップ、チャーリー・ワッツ、クリーデンス・クリアウォーターや有名人がときたま訪ねてくるんだって。で、僕が撮った写真を送っていたのを見て、俺たちもなにかしなきゃなとなったらしい。それでお墓を作ったらしいよ。」
最後に若い人に向けて、さらにはこの本に対するメッセージをいただいた。
「この写真(『Cotton Fields』)からは歌は聞こえてこないけど、音は聞こえてくるよ。」